日本人になじみの深いお香。神社やお寺でお香をたいたことがある人も多いのではないかと思います。お香の中で一番身近で手軽なものは直接費をつけて使うタイプのお香です。
今回はそんな火をつけて使うタイプのお香のタイプ別特徴についてみていきたいと思います。

スティック型、コーン型、渦巻型…、お香のタイプ別特徴について。
火を使うお香のタイプは大きく分けると3種類あります。それぞれのタイプ別特徴についてみていきたいと思います。
- スティック型
- コーン型
- うずまき型
スティック型お香の特徴
スティック型のお香は一番よく見かける棒状のお香です。一定の強さで香りを放ちます。
コーン型お香の特徴
コーン型のお香は円錐形の形をしているお香です。燃焼時間は比較的短く短時間で香りを広げたいときに使用します。
うずまき型お香の特徴
うずまき型のお香は長時間の間お香をたくこをとを目的に作られています。もともとはお通夜の際、線香を12時間たき続けられるようにと作られたものと、日本では定番の蚊取り線香のようにうずまき型に型押しして作られたタイプがあります。
焼香、抹香など上記以外のお香タイプの特徴について。
火を使うお香のメインのタイプは上記のような固形のものがおおいです。ですがそれ以外にも、直接香料や香木の破片を燃やして香りを焚いたり、粉末上のお香のタイプも存在します。
- 焼香
- 抹香
焼香の特徴
焼香とは、葬式などの仏事で弔いのためにお香をたく行為のことをいいます。お香には今回ご紹介したように様々なタイプのものが存在ます。そのなかでも焼香は儀式の名前とは別に。焼香のために刻んで用意された香料のことを総称して焼香と呼ぶようになりました。お葬式や仏壇にある細かな木片のことを焼香といいます。
一般的に焼香には、沈香、白檀、丁字、 麝香、 龍脳という五種香というものが使用されることが多いのですが。使われる香料の数によって「三種香」 「五種香」 「七種香」 「九種香」 「十種香」とくべつされています。
抹香の特徴
抹香は焼香の一種ですが、粉末状のお香のことを総称して抹香と呼びます。
火を使うお香についてのまとめ
いかがでしたでしょうか。一般的に火を使うお香は大きく分けると今回ご紹介したタイプがメインとなります。そのほかにも、火を使わずに香りを楽しむお香などありますので是非様々な香りの楽しみ方を試してもらえればとおもいます。



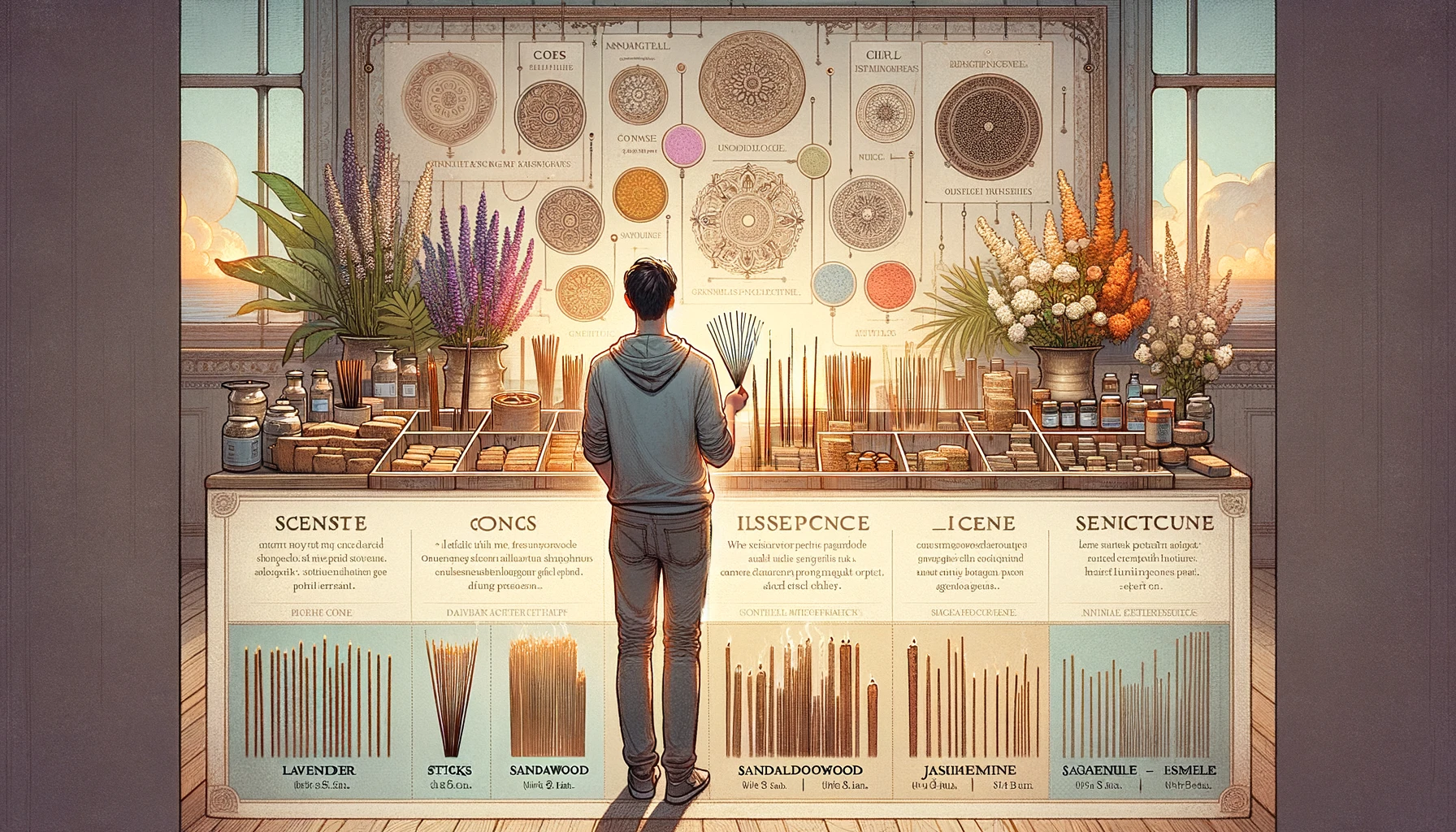















この記事へのコメントはありません。